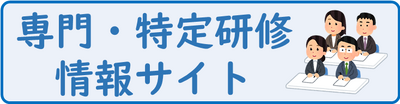令和6年度・専門研修一覧
| 番号 | 22 |
|---|---|
| 分類 | 教育の情報化 |
| タイトル | 授業で使えるICT研修会 |
| 育成する力 | ICT活用指導力 |
| 目的 |
学習指導要領では、情報活用能力が「学習の基盤となる資質・能力」と位置付けられ、その育成のために必要なICT環境を整え、それらを適切に活用した学習活動の充実を図ることが求められています。 本研修では、scratchの第一人者、阿部和広氏を講師にお招きし、最新のプログラミング教育の動向についての講演や演習等を通して小学校プログラミング教育の理解を深めるとともに、現役教員による各教科でのICTを活用した授業実践の講義を行い、授業で使える情報活用能力を育成します。 |
| 研修内容 |
講義:プログラミング教育の概要、ICT活用事例発表 演習:プログラミング教材の体験 |
| 対象 |
小学校 中学校 高等学校 特別支援学校 |
| 番号 | 31 |
|---|---|
| 分類 | 生徒指導・教育相談 |
| タイトル | みんなで考える 生徒指導・教育相談 |
| 育成する力 | 組織的課題解決力 |
| 目的 | いじめ、不登校、発達障害への理解・対応や学校内外との連携の在り方など、総合的な生徒指導の力量を高めるととも、校内の生徒指導、教育相談体制づくりについての組織的課題解決力を育成します。 |
| 研修内容 |
第1日 講義:いじめに対応する学校組織づくり~未然防止から重大事態まで~ 講師:千葉大学 教育学部 教授 藤川 大祐 氏 第2日 講義:不登校児童生徒への支援~子ども達の学びを支える~ 講師:埼玉県立大学 保険医療福祉部 教授 東 宏行 氏 第3日 講義:多様な児童生徒を支える~発達支持的生徒指導~ 講師:文教大学 教育学部 教授 会沢 信彦 氏 演習:発達障害に関する相談の対応 レポート協議:発達障害が疑われる児童生徒への対応 |
| 対象 |
小学校 中学校 高等学校 特別支援学校 |
| 番号 | 46 |
|---|---|
| 分類 | 管理職 |
| タイトル | 管理職・学校の危機管理研修会 |
| 育成する力 | 組織的推進力 リスクセンス 災害発生時の対応力 |
| 目的 | 学校は、管理職のリーダーシップの下、児童生徒や教職員の生命や心身等の安全を確保することが重要です。本研修では、学校が備えるべき「危機管理」について専門家から学びリスクセンスを高めていきます。 |
| 研修内容 |
・1日目 講義:学校事故・いじめの対応等に係る最近の動向等について 講師:つむぎ法律事務所 弁護士 梅田 沙知 氏(スクールロイヤー) 協議:協議題は研修日の1週間前程度に専用サイトにて公開 ・2日目 講義:災害経験から学んだ校長としての取組(仮) 協議:講義内容を踏まえた協議題を予定しています。 講師:熊本県市立小学校 元校長 武永 春美 氏 1日目は、教育裁判例等を参考にリスクセンスを高め、組織的な体制の構築など、事故やトラブルの未然防止について学びます。 2日目は、災害発生時の初期対応等に係る講義と、協議等を通した避難所運営のシミュレーションを行います。多くの学校が災害発生時の避難所を兼ねていることから、災害対応のサイクルと防災対策の基本、避難所運営の要点等について学びます。 |
| 対象 |
小学校 中学校 高等学校 特別支援学校 |
| 番号 | 45 |
|---|---|
| 分類 | 管理職 |
| タイトル | 「探究的な学習」に本気で取り組む 学校マネジメント研修会 |
| 育成する力 | 課題解決力 マネジメント力 |
| 目的 | 高等学校においては「探究的な学習」が学習指導要領改訂の中心的なキーワードとなっています。本研修では、「総合的な探究の時間」や「探究」を科目名に組み入れた新科目等の授業の充実により、生徒の自ら考える力を養う学校づくりにつながるマネジメント力を育成します。 |
| 研修内容 |
・第1日 講義演習:「総合的な探究の時間」の充実(仮) 講 師:お茶の水大学 特任講師 植竹 紀子 氏 ・第2日 講義演習:探究活動に伴う図書館の活用 講 師:県立学校司書教諭 講義演習:実践事例報告 講 師:県立学校管理職 |
| 対象 |
高等学校 特別支援学校 |
| 番号 | 44 |
|---|---|
| 分類 | 管理職 |
| タイトル | 管理職・ICT活用研修会 |
| 育成する力 | ICT活用指導力・組織的推進力 |
| 目的 |
教育デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進は第4期教育振興基本計画の基本方針の一つに挙げられています。 この研修では教育DXに関する国の動向や先進的に取り組んでいる自治体等の事例等について知り、教育DXに関する理解を深めるとともに、自校の課題解決に向けたICT活用指導力と組織マネジメント力を、講義と演習から育成します。 |
| 研修内容 |
・講義:第4期教育振興基本計画と教育DXの推進(仮称) ・演習:業務フロー作成の意義と活用(仮称) |
| 対象 |
小学校 中学校 高等学校 特別支援学校 |
| 番号 | 41 |
|---|---|
| 分類 | 生涯学習 |
| タイトル | 読書活動推進講座 |
| 育成する力 | 読書技法についての知識や技能 |
| 目的 |
子供たちが本に親しみ、読書体験を豊かにすることは、読書習慣を身に付け読解力の基礎を育む上で重要です。 本研修では、子供たちに豊かな読書体験を提供することを目指し、読書技法についての知識や技能を、専門的な講義や受講者同士の演習を通して育成します。 |
| 研修内容 |
・第1日 講義演習:豊かな読書活動に向けた学び(仮) 講 師:県立学校司書教諭 ・第2日 講 義:読み聞かせの基本を学ぼう ~本の持ち方・読み方・選び方~ 演習協議:読み聞かせのブラッシュアップ ~読み聞かせ実技演習~ 講 師:埼玉県立図書館おはなしボランティア指導者 |
| 対象 |
幼稚園 小学校 中学校 高等学校 特別支援学校 |
| 番号 | 40 |
|---|---|
| 分類 | 生涯学習 |
| タイトル | 地域とともに歩む学校づくりセミナー |
| 育成する力 | 地域連携に関する知識や活用力 |
| 目的 |
「よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創る」という目標を学校と社会が共有し、子供たちの資質・能力を育む「社会に開かれた教育課程」の実現に向け、地域と学校の連携・協働を推進していくことが重要です。 本研修では、学校・家庭・地域が一体となった教育活動を推進することを目指し、地域連携に関する知識や活用力を講義や演習から育成します。 |
| 研修内容 |
(予定) ・第1日 講義演習:コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進 講 師:国立教育政策研究所 社会教育実践センター職員 ・第2日 講 義:社会教育施設と学校の連携で育つ子供 講 師:青山学院大学 教授 山本 珠美 氏 講義演習:県立博物館の実践紹介 ・特別史跡埼玉古墳群見学 講 師:県立博物館職員等 |
| 対象 |
小学校 中学校 高等学校 特別支援学校 |
| 番号 | 39 |
|---|---|
| 分類 | 生涯学習 |
| タイトル | 埼玉県著作権講習会 |
| 育成する力 | 著作権の基礎的な知識 運用における対応力 |
| 目的 |
近年の急速なICT化やメディアのデジタル化により、著作権を取り巻く状況は大きく変化しています。学校等における著作権の取扱い方や、基礎知識を学ぶことはオンライン学習等を進めていく上で不可欠となってきています。 本研修では、児童生徒・県民に対する著作権についての教育活動の充実や県民サービスを目指し、著作権の基礎的な知識、運用における対応力を講義や演習を通して育成します。 |
| 研修内容 |
・講義:学校教育における著作権とその取扱いについて(仮) 講師:日本複製権センター理事長 川瀬 真 氏 ・協議:著作権Q&A(仮) |
| 対象 |
幼稚園 小学校 中学校 高等学校 特別支援学校 その他 |
| 番号 | 38 |
|---|---|
| 分類 | キャリア形成 |
| タイトル | 男女共同参画推進・キャリアアップセミナー |
| 育成する力 | マネジメント力 リーダーシップ |
| 目的 | 教職員が目指すべき姿やその実現のために身に付けたい能力、経験等を整理し、主体的に自身のキャリアについて振り返ります。本研修では、今後、学校運営の推進者となろうとする教職員を対象とし、男女共同参画の現状を学び、ロールモデルとなる学校管理職経験者等の体験談等を聞いていただきます。そして、少人数グループによる協議等を通じて自分自身を振り返るとともに、マネジメント力やリーダーシップ力を育成します。 |
| 研修内容 |
・第1日 講義:男女共同参画の視点に立った学校づくり 講師:国立女性教育会館(NWEC) 講義:採用から現在までで大切にしてきたこと(仮) 講師:教育局職員又は県立学校管理職経験者(仮) 協議:(講義の内容を踏まえたテーマを予定しています) ・第2日 講議:ミドルリーダーに期待すること(仮) 講師:教育局職員又は県立学校管理職経験者等 協議:自身のキャリアプランについて ※行政職の仕事内容等も紹介する予定です。 指導者:教育局職員又は県立学校管理職経験者等 ※第2日までにキャリアプランシートの作成があります。 |
| 対象 |
高等学校 特別支援学校 |
| 番号 | 37 |
|---|---|
| 分類 | マネジメント |
| タイトル | 教諭等・学校組織マネジメント研修会 |
| 育成する力 | 組織マネジメント力・ファシリテーション力 |
| 目的 |
各学校で中核となる人材に対し、学校における組織的なマネジメントの手法に係る講義・ファシリテーションに関する演習・協議を行い、体系的な学校運営の方法を学びます。 本研修では、学校内外の能力・資源を活用し、学校教育目標を達成していく過程(活動)で、学校をよりよくしていくための組織マネジメント力を育成します。 |
| 研修内容 |
講 義:学校改革組織マネジメント セッションⅠ:ファシリテーターの役割と進め方 セッションⅡ:世代を結ぶ協働探究のコミュニティ 【その他】 ・詳細は後日案内予定 |
| 対象 |
高等学校 特別支援学校 |
| 番号 | 32 |
|---|---|
| 分類 | 生徒指導・教育相談 |
| タイトル | 教育相談・カウンセリング研修会 |
| 育成する力 | 教育相談力 |
| 目的 | 児童生徒・保護者が抱える様々な課題について理解を深め、関わり方について学び、教育相談に関する知識・対応力を高めます。 |
| 研修内容 |
第1日 講義:教育相談に関すること① 児童生徒・保護者相談対応・カウンセリングに関すること 講師:東京家政大学 心理学部 教授 杉山 雅宏 氏 第2日 講義:教育相談に関すること② 子供の発達理解 講師:奥山子どもクリニック 理事長兼院長 奥山 力 氏 【その他】 ・20年経験者研修の読み替えについて 20年経験者研修の受講対象者は、幼・小・中・高・特になります。 |
| 対象 |
幼稚園 小学校 中学校 高等学校 特別支援学校 |
| 番号 | 24 |
|---|---|
| 分類 | 教育の情報化 |
| タイトル | 3Dモデリング研修会 |
| 育成する力 | ICT活用指導力 |
| 目的 | 3Dモデリング等に関する基礎的な知識及び活用技術を演習により学び、3Dプリンタやレーザー加工機を活用した教材の作成能力を育成します。 |
| 研修内容 |
講 義:知的財産権について 演習①:オンラインサービスを活用した3Dモデリングの基礎 演習②:レーザー加工機を活用した造形技術の基礎 【その他】 演習①においてgoogleアカウントを使用します。ご自身でお持ちのアカウントをご確認ください。(アカウントをお持ちでない方は当センターより限定アカウントを貸与します。申し込みの際に備考に「アカウント貸与希望」と記載してください。) |
| 対象 |
小学校 中学校 高等学校 特別支援学校 |
| 番号 | 14 |
|---|---|
| 分類 | 日本語指導 |
| タイトル | 多文化共生を目指した日本語指導法講座 ~日本語指導が必要な児童生徒のために~ |
| 育成する力 | 実践的な日本語指導力 |
| 目的 | 日本語指導が必要とされる児童生徒のために、日本語指導に必要な知識・技能を身に付けるとともに、実践的な日本語指導力の育成を目指します。 |
| 研修内容 |
講義演習:日本語の指導~現場知の実践~ 外国人児童生徒のためのJSL対話型アセスメント(DLA)の活用 協 議:所属校における日本語指導の方法と課題 |
| 対象 |
小学校 中学校 高等学校 特別支援学校 |
| 番号 | 13 |
|---|---|
| 分類 | 国際理解 |
| タイトル | 国際理解教育実践研修 ~SDGsと多文化共生の視点による~ |
| 育成する力 | 多文化共生に係るファシリテーション力 |
| 目的 | グローバル化が進む現在、国際理解教育やSDGsについての理解を深めることが求められています。本研修では、JICAによる「SDGs」や「多文化共生プログラム」についての講義と演習を通して、多文化共生に係るファシリテーター力 を育成します。 |
| 研修内容 |
講義:JICAにおける国際理解教育の取組 見学:JICA地球ひろばサテライト展示の見学 演習:多文化共生プログラム |
| 対象 |
小学校 中学校 高等学校 特別支援学校 |
| 番号 | 12 |
|---|---|
| 分類 | 外国語 |
| タイトル | 小学校外国語専科指導教員による魅力ある授業づくり研修会 |
| 育成する力 | 授業構想力・ICT活用指導力 |
| 目的 | 専科指導教員が互いに日々の授業実践を共有し、それぞれが抱える悩みや課題を受講者同士で解決策を見出しながら、国や県の動向をおさえた授業改善を図り、自信をもって授業に臨むことを目指します。 |
| 研修内容 |
・第1日 講義演習:「小学校外国語教育の現状と課題」 講 師:義務教育指導課 指導主事 ・第2日 講義演習:「小学校外国語活動・外国語の授業におけるICTの効果的な活用」 講 師:文部科学省初等中等教育局教科書課デジタル教科書企画係 【その他】 ・事前課題 第1日目に使用する。課題言語活動の充実を図った実践事例と評価規準例についてA4片面1枚程度にまとめる。 ・ミーティングID及びパスコード 後日「日程及び内容等」に記載します。 |
| 対象 |
小学校 中学校 高等学校 特別支援学校 |
| 番号 | 9 |
|---|---|
| 分類 | 図工・美術 |
| タイトル | 美術館を利用した図工・美術鑑賞授業づくり研修会 |
| 育成する力 | 鑑賞に対する実践的指導力 |
| 目的 | 実践に生かせる鑑賞の授業づくりを目指し、美術館の教育普及活動や鑑賞プログラムの紹介や鑑賞活動に対する実践的指導力について、講義、演習及びワークショップを通して育成します。 |
| 研修内容 |
講義:美術館の教育普及活動 演習:美術館を利用した授業づくり 参観:ワークショップ:ドローイング ※埼玉県立近代美術館の教育普及担当者による鑑賞指導を体験し、実践に生かせる鑑賞授業作りをグループで行います。 ※昨年度と同様の内容で予定しています。 |
| 対象 |
小学校 中学校 高等学校 特別支援学校 |
| 番号 | 5 |
|---|---|
| 分類 | 音楽 |
| タイトル | 「楽しい授業づくり」音楽科研修会Ⅱ |
| 育成する力 | 合理的配慮を踏まえた指導力 |
| 目的 | 音楽科の授業でも、児童生徒一人一人に合った「個別最適な学び」が求められています。本研修では、音楽科の学びの過程において考えられる困難さに対する指導の工夫を一緒に考えることを目指します。「特別支援教育の視点からの音楽教育」についての一人一人の教育的ニーズに応じたきめ細かな合理的配慮を踏まえた指導力を、様々な支援の仕方や教材教具の紹介等から育成します。 |
| 研修内容 |
講義演習:特別支援教育の視点からの授業実践紹介と教材研究 特別支援教育の視点からの授業展開と事例演習 |
| 対象 |
小学校 中学校 高等学校 特別支援学校 |
| 番号 | 11 |
|---|---|
| 分類 | 外国語 |
| タイトル | 外国語教育における小・中・高等学校の接続を重視した授業力向上研修会 |
| 育成する力 | 授業構想力 |
| 目的 |
学習指導要領では小学校、中学校、高等学校の接続に留意しながら、学びの連続性を意識した指導の充実が求められています。 本研修では、各校種における外国語活動や外国語科の内容、指導等の実態を把握することにより、小学校から中学校、中学校から高等学校への円滑な接続を図ることで、共通の目標である「言語活動を通して外国語によるコミュニケーションを図る資質・能力を育成すること」を目指します。受講者による協議を中心とした研修を通して、外国語活動・外国語科における授業構想力を育成します。 |
| 研修内容 |
第1日 協議:各校種における授業の現状と言語活動の充実 第2日 協議:授業におけるICTの活用と観点別評価の工夫 |
| 対象 |
小学校 中学校 高等学校 |
| 番号 | オンライン連携講座6 |
|---|---|
| 分類 | 特別支援教育 |
| タイトル | 特別支援学校・特別支援学級における授業づくり講座 ~思春期・青年期の知的障がいのある子どもの自立活動をメンタルヘルスの視点から考える~ |
| 育成する力 | |
| 目的 | 知的障がいのある子どもの思春期・青年期におけるメンタルヘルスの不調に関する基本的情報について学び、事例などを基に理解を深める。また、学校現場において実際に指導・支援を担う教職員の役割について考える。 |
| 研修内容 | |
| 対象 |
小学校 中学校 高等学校 特別支援学校 |
| 番号 | オンライン連携講座5 |
|---|---|
| 分類 | 特別支援教育 |
| タイトル | すべての教職員に役立つ!支援につながる子どもの理解講座~子どもの願いに寄り添うための教師の基本姿勢~ |
| 育成する力 | |
| 目的 | 通常の学級等における特別な支援を必要とする子ども一人一人の学びの保障の視点から、子ども理解に努め、子どもの願いに寄り添ったかかわりと支援について学び、実践に生かそうとする態度を身につける。 |
| 研修内容 | |
| 対象 |
小学校 中学校 高等学校 特別支援学校 |